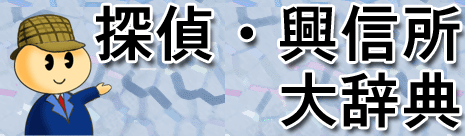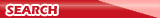 |
サイト内検索 |
|
|
|
| |
|
| 離婚の概要
日本において離婚に関する規定は、民法(明治29年法律第89号)第763条から第771条に設けられている。離婚の手続き規定として、戸籍法(昭和22年法律第224号)、家事審判法(昭和22年法律第152号)、人事訴訟法(平成15年法律第109号)が存在する。
離婚の種類
規定されている離婚の種類として、協議離婚(協議上の離婚)、調停離婚、審判離婚、裁判離婚(裁判上の離婚)が存在する。
◎協議離婚
夫婦の間で、離婚について協議し、お互いに合意する事ができれば、裁判所を介さず出来る離婚を「協議離婚」と言う。日本においての離婚の殆どが、この協議離婚である。
<協議離婚に関する条文>
夫婦はその協議で、離婚をすることができる(第763条)。
ただし未成年者の子がある場合は親権者を決める必要がある(819条第1項)。
夫婦双方の合意が必須となるため、夫婦の一方が勝手に離婚届を作成して提出した場合、文書偽造罪で罰せられ、離婚は無効となる。また、配偶者の親との間で養子縁組をしている場合は、養子離縁届を出さない限り、前配偶者とは義兄弟姉妹の関係が残り、前配偶者の親族の間で親族関係が続く。
離婚をした者の一方は、相手方に対して財産分与を請求することができる(768条)。
協議離婚で、子供や孫がいる場合であっても、養育費について夫婦間でしっかりとした取り決めがなされない場合が多いが、後になってから後悔する事のないように、離婚給付等契約公正証書を作成するべきである。その中の項目として、金銭の支払いに関しての、強制執行認諾条項を付けて加えておけば、支払い義務のある者が債務を履行しない場合に、強制執行によって、その者の不動産、動産、給料等を差し押さえる事が可能となるのである。
◎調停離婚
協議離婚で話し合いが付かなかった場合、家庭裁判所で調停する。
その調停で決定した離婚を「調停離婚」と言う。
<調停離婚に関する条文>
離婚の訴えを提起しようとする者は、まず家庭裁判所に調停の申立てをしなければならない(同法18条、17条)。これを調停前置主義という。
家庭裁判所の調停において、夫婦間に離婚の合意が成立し、これを調書に記載したときは、離婚の判決と同一の効力を有する(家事審判法21条本文)。
◎審判離婚
「調停離婚」で話し合いがつかなかった場合、裁判所に離婚の判断をゆだね「調停に代わる審判」で成立する離婚を「審判離婚」と言う。但し、2週間以内に当事者から異議の申し立てがあると効力を失うことになる。意義の申し立てがない場合は離婚は成立する。
<審判離婚に関する条文>
調停が成立しない場合であっても、家庭裁判所が相当と認める場合、職権で離婚の審判をすることができる(家事審判法24条1項前段)。
2週間以内に家庭裁判所に対する異議の申立てがなければ、その審判は、離婚の判決と同一の効力を有する(同法25条3項、1項)。
◎裁判離婚
裁判離婚の成立は殆どなく、離婚総数の1%程度と言われている。
「裁判離婚」とは、「協議離婚」、「調停離婚」において話し合いがまとまらず、審判離婚が成されない時に、判決によって離婚することで、法的強制力を持つものである。
<裁判離婚に関する条文> 民法第770条
夫婦の一方は、以下の場合に限り、離婚の訴えを提起することができる。
配偶者に不貞な行為(不貞行為)があったとき。
配偶者から悪意で遺棄されたとき。
配偶者の生死が3年以上明らかでないとき。
配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき。
その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき。
裁判所は、前項第1号から第4号までに掲げる事由がある場合であっても、一切の事情を考慮して婚姻の継続を相当と認めるときは、離婚の請求を棄却することができる。
離婚をした者の一方は、相手方に対して財産分与を請求することができる(771条、768条)。
離婚の訴えは、家庭裁判所の管轄に専属する(人事訴訟法4条1項、2条1号)
離婚の訴えに係る訴訟において、離婚をなす旨の和解が成立し、又は請求の認諾がなされ、これを調書に記載したときは、離婚の判決と同一の効力を有する(同法37条、民事訴訟法267条)。
その他の離婚
◎家庭内離婚
離婚届の提出はなされていないが、夫婦関係に破綻がきたしているにもかかわらず、何らかの理由で同居生活をおくっている状態。
◎熟年離婚
一般的に結婚生活を20年以上続けてきた夫婦の離婚の事を、「熟年離婚」といい、2007年の年金制度の変更により、実際の離婚件数の爆発的増加には繋がらなかったものの、相談件数は急増し、熟年離婚を題材としたドラマも制作された。
◎ペーパー離婚
30年程前に出現した「書類上の離婚」の事で、実際の生活においては、結婚しているときの生活と同じ「事実婚」状態の事を言う。
離婚理由
司法統計年報によれば、離婚申立ての動機別順位で、夫婦に共通して最も多かったのは「性格の不一致」で、それに次いで妻側の理由として「夫の暴力」「夫の異性関係」が続くことになる。又、夫側の理由として「妻の異性関係」「妻の浪費」が続いている。
|
|
|
|